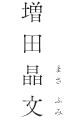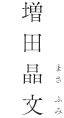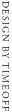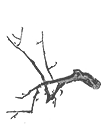








スズメの親子
今朝も、小さな庭がかまびすしい。
息をこらし、そっと、そ~っとカーテンを引く。来訪者たちは窓越しであっても、人の気配を感じるといっせいに飛び去ってしまう。あくまでも、どこまでも、慎重に。
スズメに餌をやるようになって、半年ちかくになろうか。レンガ色をした、ちっちゃな素焼きの皿に生米を盛る。皿は、毎年行事となっている、日本酒「大信州」の蔵の面々と伊勢神宮に参拝した際のものだ。お神楽を奉納し、直会(なおらい)をいただくときに使ったものを、毎回かしこまって持ち帰ってくる。
米は2007年産のカリフォルニア産のコシヒカリ。月刊誌「文藝春秋」に、アメリカや中国産のブランド米が、いずれ日本産の脅威となる――というテーマで書こうと手に入れたものだ。
しかし企画は消え、編集者とも疎遠となり外米だけが残った。アメリカン・コシヒカリの風味を気にしつつも、なんとなく食べる気にならず年月だけがたってしまった。
スズメはチョンチョンと小さくホップしながら皿の周りに近寄ってくる。
チュンチュンと大騒ぎなのは冒頭に書いたとおり。この野鳥の語源が、「チュンチュン」とさえずる「メ(小鳥の意)」というだけのことはある。合唱ではなく次々と声を重ね輪唱していく。源泉から湯水がどくどくと後から後から湧き出ていく様子にも似ている。
米をついばむ様子は十鳥十色。
数羽が仲良く頭を皿に突っ込んでいるときもあれば、隣にきたのを追い払うものがいる。中には大きく羽を広げて威嚇し、皿を独占する強硬派も。
初夏の頃には、えらくビッグサイズのがきて、皿の周りをウロウロしていた。おっかけ、小さなのが飛来し、米をつついては大きなやつの嘴にもっていく。大きなのは、甘えきって次を催促している。
ハハン、こりゃ親子だと見当をつけたのだが、よくみれば大きな子は、にこ毛のおかげで着ぶくれしているのだった。小さな親は茶と白の地味な色合いだが、羽は刃物のように堅そうだし、しっとり落ち着いた光をはなっている。
スズメの子といえば、大学の後輩S君が、巣から落ちたヒナをひろって育てていたことを思い出す。感心なことに、彼は粟や稗を乳鉢と乳棒を使いていねいに摺り、ピンセットに挟んでヒナにやっていた。
「ピーコ、ほれ、ごはんだよ、ほれ」
彼は唇を嘴のように尖らせていたが、見ているこっちもついキスするときみたいになってしまう。
S君は部室や教室、居酒屋にまでピーコを帯同していた。私の大学にはけっこう奇人変人がいたが、さすがに鳥カゴを抱え、乳鉢持参でキャンパスを行き来していたのは彼くらいだった。
「だって先輩、ヒナは30分に一回は餌をやらんと死んでしまうんです。フンの始末もしてやらんとアカンし」
この説得力あるプレゼンは、担当教官の心をも動かし(S君は工学部だった)、実験中も彼だけ30分に1度の餌やりをみとめてもらっていた……。
アッパレなことに、笹本君はピーコを育てあげた。
しかも。こう宣言したのだった。
「そろそろピーコを自然に返そと思います」
キャンパスの南隣、京都御所で籠から出されたピーコはキョトンと育ての親をみつめている。
「ほれ、飛んでけ。飛べってば!」
S君がけしかける。ピーコは小首をかしげたり、足元の砂利をつついたり。ついぞ、羽ばたく気配はない。
「アカンわ。飛ぶ練習なんかしてへんのやろ」
「いや、下宿で何度か特訓したんです」
「やっぱし、焼き鳥にすんのが正解やな」
「先輩、アホなこといわんといてください」
と、そのとき――ピーコが羽ばたいた。実に頼りない飛び方で、こっちがハラハラする。数メートル先に着地したピーコは首だけクルリっと回す。
S君と小鳥の眼があった。
次の瞬間、スズメはチッチッチッチッとスタッカートで鳴きながら再び空にむかった。
「ピーコ! ピーコ!」
S君が叫びながら走る。スズメの子は、それを振り切るかのように長々とつづく御所の塀沿いに飛んでいく。
たちまちピーコの姿が消え、S君は小さな点になった。
「…………」
しばしア然としていた私だが、とにかく足元にころがる鳥籠を拾いあげ、よたよたと親子のあとを追ったのだった。
029
澤田酒造と「白老」をめぐって(下)
028
澤田酒造と「白老」をめぐって(中)
027
澤田酒造と「白老」をめぐって(上)
026
まったく新しいHP、ちっとも変らぬ増田晶文
025
奈良で、ころがる。
024
書き下ろし小説、増田晶文は悶絶。
023
出木杉クンとのび太
022
改めて、壇一雄。
021
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』
ふたつめの「あとがき」020
おさけの「気」のご縁
019
マンガ『いっぽん!! しあわせの日本酒』コラボのお酒! 発売
018
FM PORT 「はずのみ」に出演 (にいがた県民エフエム)
017
マンガ「いっぽん!! しあわせの日本酒」連載スタート!
016
『エデュケーション』裏あとがき
015
北斎と歌麿、蕪村に若冲。
そして春町、政演。014
ポジティブ宣言
013
銘酒「笑福亭松喬」
012
大分紀行1「フグの至福」
011
スズメの親子
010
母と俳句
009
四の月
008
Song Of The Wind
007
四月に生まれて、春のこと
006
ビーがいた日
005
幼い兄妹
004
デュエイン・オールマンの追憶4
003
デュエイン・オールマンの追憶3
002
デュエイン・オールマンの追憶2
001
デュエイン・オールマンの追憶1
Design & Development by Timeoff.