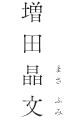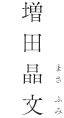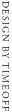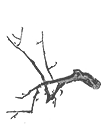








改めて、壇一雄。
小説家は布団から這いでると、
まずビールの小瓶を手にする。
唇の泡をぬぐい、ひとごこちつけば、
おもむろに買い物かごを腕へひっかけ市場へ繰りだす。
作家は分厚いメガネの奥を炯々とひからせ、
食材えらびに熱中、帰宅と同時に
盛大なる精力をもって料理にとりかかる――
壇一雄に興味を持ったのは、
こんな一文と彼の写真が載った記事をみたからだった。
作家という存在にあこがれ、いつか自分もきっと。
そんな想いを焦がしていただけに、
壇の日常は妙なリアリティと過剰な刺激、
そして憧れをもって私に突き刺さった。
この雑誌、ひら綴じオールカラーの立派な
一冊だったから「太陽」あたりだと思うのだけど、
なぜか書棚を探しても見あたらない。
そして、あれはいつの頃だったのだろう。
京都にいた大学時代か、
それとも社会人になって東京に出てきてから?
昨年(2016)の冬、壇の代表作『火宅の人』を読み返した。
彼の料理エッセイを二子玉川の蔦屋家電で手にとり、文体の明るさテンポの良さを再発見、これはたいへんな作家だと認識を新たにした次第。 家に戻るや、おっとり刀で彼の遺作のページをめくったというわけ。
『火宅の人』は悲惨な物語に違いない。
私小説というジャンルに放り込まれる作品であり、発表当時は暴露本ともいわれたのもうなずける。主人公の桂はそのまま壇と重なり、作中の人物がほぼ特定できる。
あるいは、自堕落な中年男のヨタ話といえよう。それを裏がえせば、自制のきかぬオッサンの不行状でもある。
主人公は2度目の妻とたくさんの子(次男は重度の障がいを持つ)を打っちゃり、10年近くも愛人と暮らす。 いや「打っちゃり」と書いたが、主人公はのうのうと妻子のいる家と愛人の間を行き来する(右往左往というほうが正しいか)。
その間にも、ふらりと旅立ち音信不通となる――旅先ではまたぞろ別の女と情交をつうじる。こんなことの繰り返し。
久しぶりに、気まぐれに家庭へ
顔を出した父親に子どもたちはいう。
「チチ、もうどっこも行く?」
その声の無邪気さ、妙な明るさ。普通なら、
「もうどこにも行かない?」
と心細げに問うはずなのに。
カネは懐にあるだけを、ためらいなしに使いはたす。 マネープランなんか、あったもんじゃない。 あげくに、出版社や新聞社から前借りする。
昭和50年代、主人公は新聞小説をはじめ数々の連載を持ち、月収はたびたび100万円をこえていた。 大卒のサラリーマンの初任給が7万円ちょっとだった時代のことだ。
旅先では気の置けない、どこかうらぶれた宿にこだわり、食と飲にはとめどない意欲を示す。寝床にまでウイスキーを持ちこみ、とめどなく流し込む。
主人公は初老といわれる年齢になっても女体に執着し、それがなまなかではない。 女のいない夜の寂寥は主人公の甘えであり、胸に空いた深く冥い洞でもある。独り寝すれば女への恋慕に苛まれ、己で精を散らす。 そんな時につぶやく愛への考察は崇高だが、諦観と自虐がついてまわる。
妻、愛人、時々の恋人……女たちもこんな男に愛想尽かしをすればいいものを、ずるずる泥沼にはまっていく。 彼女らにとって主人公は宿痾といってよかろう。
『火宅の人』は壮大なリフレインだ。 女の間を揺れ動く主人公。その隙間を旅と酒、食べ物で埋め尽くす。 束の間の平安と、それがもたらす強烈な反作用。主人公は「危険!」の標識がたっていたら、結局は突っ込んでいく。
激情、直行に悔恨、わがまま、反省そして破れかぶれの無限ループ。 このパターンが延々と繰り返される。
だが、壇の筆は決して読み手を飽きさせない。
それは、小説巧者というだけでなく、
壇一雄の人間そのものに起因しているところも大きい。
男の私をしても、壇はとてもチャーミング。
壇が友なら、微苦笑をおくることはできても、
縁切りしようと思うまい。 まして女をすれば――。
彼はいじらしい。愚がつくほど真っ直ぐ。
別れ話になれば、類のない寂しく哀しげな
表情を浮かべるのだろう。とても憎めたものではない。
壇は大きな子どもなのだ。
加えて(本人も認めているように)壇は実にエネルギッシュ。
胃袋しかり肝臓しかり、性欲しかり。
その尋常ならざる膂力は、
開高健や中上健二をも凌駕するほど凄まじい。
太宰なんぞでは、とてもかなわぬレベル。
子たちへの愛、恋心の炎が燃えたつほどに、
主人公は己の業火におびえる。
だが、情念の火影に浮かぶ彼の精神は肉体、
食欲、肉欲以上に図太いのだ。
壇はたびたび、繊細をとりこもうとするが、
そんなことは土台できっこない。
そこに、彼の類のない魅力がある。
なのに、壇の文体は不思議と脂っこくない。
実に軽快、サクサクと読み進められる。
壇が気さくに語る酒池と愛憎、
自省のジェットコースターストーリー。
だからこそ『火宅の人』はおもしろい。
先の展開がわかっていても、ついページをめくってしまう。
壇一雄の人徳と溶けあうユーモア、テンポのいい軽妙さすら感じる文体。 簡潔にして情緒たっぷりの会話。 ときおり顔をだす漢語や古語は透徹しており、それらがスパイスとなって文章をひきしめる。
これぞ、あたかもテールスープをつくるが如く。
じっくり煮込み、アクをていねいにとる。肉骨だけでなく、いっしょに放り込んだ野菜のエッセンスが混然一体となる。供されるスープは透明感にあふれ、すっと舌に馴染む。だが、驚くほど奥深く幅広い味わいを醸している。しかも、ふと獣の髄から滲んだ野性が。
うまい! じつにうまい。これは癖になる。
私は改めて壇一雄に圧倒された。
「かりに破局であれ、一家離散であれ、私はグウタラな市民社会の、安穏と、虚偽を、願わないのである。かりに乞食になり、行き倒れたって、私はその一粒の米と、行き倒れた果の、降りつむ雪の冷たさを、そっとなめてみるだろう」
こう嘯く壇一雄の肩に、私はそっと手を置いてみるのだ。
029
澤田酒造と「白老」をめぐって(下)
028
澤田酒造と「白老」をめぐって(中)
027
澤田酒造と「白老」をめぐって(上)
026
まったく新しいHP、ちっとも変らぬ増田晶文
025
奈良で、ころがる。
024
書き下ろし小説、増田晶文は悶絶。
023
出木杉クンとのび太
022
改めて、壇一雄。
021
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』
ふたつめの「あとがき」020
おさけの「気」のご縁
019
マンガ『いっぽん!! しあわせの日本酒』コラボのお酒! 発売
018
FM PORT 「はずのみ」に出演 (にいがた県民エフエム)
017
マンガ「いっぽん!! しあわせの日本酒」連載スタート!
016
『エデュケーション』裏あとがき
015
北斎と歌麿、蕪村に若冲。
そして春町、政演。014
ポジティブ宣言
013
銘酒「笑福亭松喬」
012
大分紀行1「フグの至福」
011
スズメの親子
010
母と俳句
009
四の月
008
Song Of The Wind
007
四月に生まれて、春のこと
006
ビーがいた日
005
幼い兄妹
004
デュエイン・オールマンの追憶4
003
デュエイン・オールマンの追憶3
002
デュエイン・オールマンの追憶2
001
デュエイン・オールマンの追憶1
Design & Development by Timeoff.