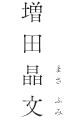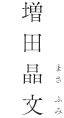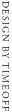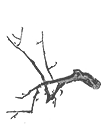








『稀代の本屋 蔦屋重三郎』
ふたつめの「あとがき」
「ほほう、歴史小説家に転身ですか?」
意味深な笑いを私に投げかける人がいる。
とんでもない!
私はさほど歴史小説にこだわっておりません。
(実際、歴史ものを書くのはあれこれと考証が必要でテマがかかる。
私のようなメンドークサがりにとっては、しんどい作業の連続なのだ)
問いの奥にあるものは、簡単に見透かせる。
いわずもがな、歴史小説は当代きっての人気ジャンル。
本書もまたその一角に紛れ込まざるをえない。
「売れるっていうんで歴史モノをやるんだろ」
私は、こんなスガメをはねかえす勢いで申し上げる。
「果てなき渇望を抱く者あらば、それを描くのが私の業。
時代なんぞは関係なし」
草思社の藤田博さんという、デビュー作以来ご担当いただいている編集者をえて『稀代の本屋 蔦屋重三郎』は出版できた。 その経緯は本作の「あとがき」に記してある。
「渇望」は私がずっと追いかけているテーマで、主なる作品はすべてここに収斂されているとご理解いただきたい。
しかして。 私自身が抱く渇望とは?
高名、金満、うまい酒、ファッション……単なるエエカッコしい。 あまりに下卑ており、お恥ずかしいかぎり(ここんところ、いい女に興味がなくなってきた。 これまた情けない)
だが、作品の主人公には高潔かつ一途、人生を賭した願いをもっていてほしい。
蔦屋重三郎はまさしく渇望の人。
山東京伝や恋川春町らの黄表紙で江戸をわかせた。 京伝、春町はもはや日本史の教科書の中の人物で、今の世に彼らの作品が読まれることはない。
だが黄表紙という名の「大人のピクチャーブック」は江戸の一時期とてつもない人気を誇った。 そして、その書き手として大いに名を売ったのが彼らなのだ。
重三郎は浮世絵での仕事ぶりも鮮やか。
なにしろ天才歌麿の才を磨き、怪物写楽を発掘してみせた。
重三郎というのは、これはもう、とてつもない出版人なのだ。
加えて彼は吉原という街を、春をひさぐ場所から、江戸いや日本を代表するカッコいい街へと引き上げてみせた。
私くらいの年齢の方ならバブル期の渋谷パルコを思い起こしてほしい。 あの渋谷駅からずいぶん離れた坂の途中のゾーンが、いわばDCブランドの服を売っているだけのファッションビル群が、なにかしら眩しくも魅惑的なスポットに変貌していたことを。
間違いなく、当時の若者たちは、パルコにいけばなにかステキなものが、心躍ることが起こると思い込んでいた――。
重三郎は出版物を駆使して、吉原を江戸の民の憧れの地に昇華させてみせた。 その意味で、彼は世界に誇れるメディアプロデューサーでもある。
蔦屋重三郎の一生は、常に本屋という枠からはみ出ながら、新しい世の中をつくるという渇望に貫かれていた。
重三郎に出逢ったきっかけのひとつは「週刊ポスト」の江戸のエロス企画だった。
『ジョーの夢』から『エデュケーション』を経るまでの数年、私はそうやって無記名の雑誌記事を書きちらすことで糧を得ていた。
だが、私は雑誌の仕事を通じて艶本(枕絵)の奥深さにふれ、江戸の町衆の奔放でおおらかな性意識を知った。
ことに白倉敬彦さんからは、艶本を通じて江戸の出版文化についてあれこれご教示を賜った。 もちろん重三郎のこともしかり。
白倉さんはフリーのエディターとして数々の美術書を編纂、とりわけ江戸の浮世絵、春画に関して造詣が深く日本どころか世界的な研究者だった。
かような斯界の泰斗から、貴重な図版を前にして数回にわたってご教示いただけたという事実がありがたい。
しかも! 白倉さんは決して、えらそうな態度をとる方ではなかった。 いつも穏やかな笑みを浮かべ、ていねいに的を射た説明をしてくださった――このことは、ぜひとも特記せねば!
白倉さんは2014年10月4日に永眠された。 日本の浮世絵研究界にとって、まさに「巨星墜つ」の悲報であった。
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』を氏の墓前に捧げたい。
余談ながら、蔦屋重三郎はTSUTAYAのご先祖にあらず。 ツタヤは増田宗昭がファウンダー(増田姓だが私の親戚でもない)。 しかし、どこぞで読んだ記事では、氏も蔦屋重三郎の人と業績に深い興味を抱いている云々――とあったはず。 記憶違いならご寛恕ください。
3年かけて『稀代の本屋 蔦屋重三郎』を完成させたが、
ここで息を抜くわけにはいかない。
いよいよ私の筆は、もっともっとと叫んでいる。 渇望の名のもと、私を読者を震わせるようなターゲットを得て、書きたいという想いを存分に発揮せねばならぬ。
029
澤田酒造と「白老」をめぐって(下)
028
澤田酒造と「白老」をめぐって(中)
027
澤田酒造と「白老」をめぐって(上)
026
まったく新しいHP、ちっとも変らぬ増田晶文
025
奈良で、ころがる。
024
書き下ろし小説、増田晶文は悶絶。
023
出木杉クンとのび太
022
改めて、壇一雄。
021
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』
ふたつめの「あとがき」020
おさけの「気」のご縁
019
マンガ『いっぽん!! しあわせの日本酒』コラボのお酒! 発売
018
FM PORT 「はずのみ」に出演 (にいがた県民エフエム)
017
マンガ「いっぽん!! しあわせの日本酒」連載スタート!
016
『エデュケーション』裏あとがき
015
北斎と歌麿、蕪村に若冲。
そして春町、政演。014
ポジティブ宣言
013
銘酒「笑福亭松喬」
012
大分紀行1「フグの至福」
011
スズメの親子
010
母と俳句
009
四の月
008
Song Of The Wind
007
四月に生まれて、春のこと
006
ビーがいた日
005
幼い兄妹
004
デュエイン・オールマンの追憶4
003
デュエイン・オールマンの追憶3
002
デュエイン・オールマンの追憶2
001
デュエイン・オールマンの追憶1
Design & Development by Timeoff.