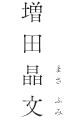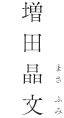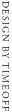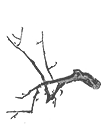








大分紀行1「フグの至福」
春、4月。大分市へいってきた。
「フグ、もうシーズンは終わったけん」
ふらりと入った寿司屋でコワモテの若い板前がいった。私はピクッと片眉を動かしたものの、沈着さを失わずにお勘定を払った。
だが、そのときの胸中たるや――。
「じゃかあっしゃい! オレは食いたいもんを食いたいときに食うんじゃい」
久しぶりのひとり旅だ。
しかも50代で最初のひとり旅(来週あたり、私は54歳になります)。
加えて、私にとって大分市は未踏の地。
男のひとり旅において、夕食のチョイスはその趨勢を左右する大問題ではある。
だが、私になんら逡巡はなかった。
「フグだ、フグ、フグ」
あの白くもっちり締まった身と、この魚ならではのあえかな香り、甘さ。フグを淡泊という御仁はトーフの角で頭を打ちつけよ。
淡麗と見せかけて、実はしっかりとした味わいがある。
身のみならず、皮よし白子よし。ひれ酒さらによし。難点は骨が多いこと。
そして、お値段(これがホンマにシビア)。
「さ、奥へどうぞ」
私より十歳は年配とおぼしいが、和服に完璧なメイクが侮れない女将に導かれ「橘の間」に入る。六畳、掘りごたつ。違い棚には、薄い桃色の洋花と紡錘形をした新芽の枝が活けてある。書院の障子紙の色目は少し橙がはいっていた。さらにテーブルには一輪ざし。
カウンター席でちんまり食すのも仕方ないと観念していただけに、個室というのがうれしい。
遠くの座敷から、男たちの笑い声が小さく聞こえるけれど特に気にはならない。
「週末ですが、たまたまこのお部屋が空いておりました。ご縁、感じますわ」
女将が世辞をいいつつ、エビスの中瓶を小体のグラスに注ぐ。
「エビス→サッポロ赤星→一番搾り→サッポロ黒ラベル→キリンラガー」とは、麦酒オーダーにおいて自ら課している厳しいヒエラルキーだ。そういえば、サッポロビールは大分県日田市にて醸されている(大阪・茨木工場閉鎖後、西日本の工場はここだけ)。
コースは2つ。フグシューマイ(2コ)とフグ寿司(2カン)がつくかつかぬかの差。シューマイはフグじゃなくてブタかエビが望ましい。寿司は昼にいただいた。酢飯を2食続けて口にする気にはならん。
「よって8400円のコースにします」
女将、艶然とほほ笑んだ。
「ウチはボリュームが凄いので、それでよろしゅうございましょう」
「酒はこれ以上呑みません。ひたすらフグをいただきたい」
「きっとご満足いただけますわ」
私、一瞬の間をおいてのべる。
「されど、ひれ酒だけは……」
女将、大年増の色香を放ちつつ横眼を使う。
「大分の地酒、とってもおいしいのがございます。ご期待あれ」
――万事、うまく進んでおるではないか。
口取りはフグ皮の肝あえ。
次いで、てっさ。かなり分厚い。薄く切れば、というか東京や大阪なら優に2人前となろう。にもかかわらず、透明感がなまなかではない。有田の皿の絵柄がちゃんと透けてみえる。
月鞘ネギを巻き、名代カボスのぽん酢にちょいとつける。
これが、いい。カボスはユズやスダチほど柑橘香は強くないけれど、あえかな果実の甘みが味わえる。
露骨な押し出しをせぬ佇まい、そこがとっても好ましい。さらに紅葉おろし。そっと舌を刺す辛み。薬味たちのハーモニーがすばらしい。
そして、肝。これを食せるのは大分だけ。3分の1くらいを切り分けポン酢に解く。そうして、てっさを食せばまた格別。肝だけ口に運べば、濃醇でコクはあれども、魚臭さ、とりわけ鼻孔に侵入し、舌にも残る劣化臭がない。
新鮮なハゲの肝もうまい。けれど、フグには一歩譲る……と今夜はいってしまおう。ハゲ、ゆるせよ。
「大分でも条例ではフグの肝を出すのはご法度ですの。けど、それを罰する規則がありませんので、オホホホホ」
女将は、わけがわかったようで、そのじつナニソレ? ってことをのたまう。私も愛想笑いで、ハアハアと適当にこたえる。
法規問題はともかく。から揚げ、これも大ぶり。シューマイと寿司、オーダーしなくてよかった。
特記すべきは、女将のあらわれるタイミング。どこぞにモニターが仕込んであるのか。実に絶妙の間合いで料理を運んでくる。
「こういう商売をしておりますと、お客さまのお箸の進み具合はわかるものなんですの」
女将はしゃあしゃあといってのけた。
続いて、てっちり。これまた堪能した。家で鍋をすれば鶏、豚、牛にかかわらず野菜へ手が伸びがちなのだが、フグだけは違う。ひたすらフグだけ食べたい(けど春菊や白菜も完食しました。私はつくづくお行儀よいオッサンなり)。
最後は雑炊、焼いた小餅をいれる。餅の焦げた匂いが鼻をくすぐる。月鞘、ポン酢を少々。さらさらと、すするがごとく掻きこむ。薄味に香の物でアクセントをつける。うまい。椀の縁まで舐めてもうまい。日本人に生まれて、ちゅーか、大分に来てよかった。冬ならもっとうまいのだろうか? でも、私にとっては、眼の前に至福があることこそ大事なのだ。
しかし、画龍は点睛を欠いた。
ひれ酒、これが……女将によれば、まことに縁起よい銘柄の大分地酒なれど。
いかんせん甘い。熱燗にして酸がいっそうたち、ツーマッチ・スイートな余韻が腔内にこびりつく。ほぼジュースやないか、これ。もう一本、苦きビールを頼んで口の中を洗いたくなるほどであった。ヒレを炙った風味とまったくあわない。
いまどきの日本酒、やたら酸がたって、フルーティーに傾く味わいが目立つ。しかも、かような果汁的甘みや薫り、ひとつの個性だけ際立った酒が評価されたりしている。しかし私にいわせれば、そんなのアンバランでしかない。うまい日本酒とは、すべての要素が高いレベルで均衡し安定しているのだ。五感の官能を充分に満たしてくれるから、どれかひとつだけ感性にひっかかることはない。
あるいは大分の地酒――たまり醤油のごとく、カボスのごとく、この「甘さ」に九州の味覚の奥義が潜んでいるのかもしれない、のかな、ホントにそうなんだろうか。わからん。 何はともあれ、ヒレ酒、1合だけの注文で助かった。
人生、おいそれと完璧にはいかない。
日本酒から、またまた浮世の在り方を教えていただいた。
「けど、フグはシーズンを外してもうまい」
さて。料亭を出れば都町、大分市随一の歓楽街。奥歯の裏に残った、気色のわるい日本酒の後味を舌でこそげ落としながら、オッサンは夜の蝶の採取をもくろむのであった。
かくして豊後の夜は、ゆるりと更けゆく。
当夜の首尾は……待て次号。
029
澤田酒造と「白老」をめぐって(下)
028
澤田酒造と「白老」をめぐって(中)
027
澤田酒造と「白老」をめぐって(上)
026
まったく新しいHP、ちっとも変らぬ増田晶文
025
奈良で、ころがる。
024
書き下ろし小説、増田晶文は悶絶。
023
出木杉クンとのび太
022
改めて、壇一雄。
021
『稀代の本屋 蔦屋重三郎』
ふたつめの「あとがき」020
おさけの「気」のご縁
019
マンガ『いっぽん!! しあわせの日本酒』コラボのお酒! 発売
018
FM PORT 「はずのみ」に出演 (にいがた県民エフエム)
017
マンガ「いっぽん!! しあわせの日本酒」連載スタート!
016
『エデュケーション』裏あとがき
015
北斎と歌麿、蕪村に若冲。
そして春町、政演。014
ポジティブ宣言
013
銘酒「笑福亭松喬」
012
大分紀行1「フグの至福」
011
スズメの親子
010
母と俳句
009
四の月
008
Song Of The Wind
007
四月に生まれて、春のこと
006
ビーがいた日
005
幼い兄妹
004
デュエイン・オールマンの追憶4
003
デュエイン・オールマンの追憶3
002
デュエイン・オールマンの追憶2
001
デュエイン・オールマンの追憶1
Design & Development by Timeoff.